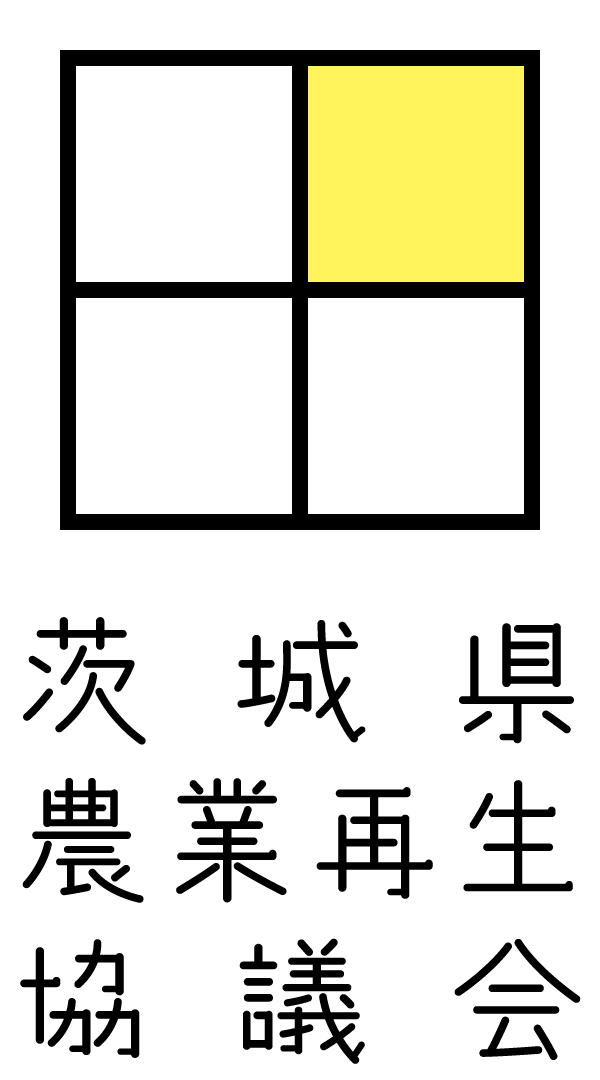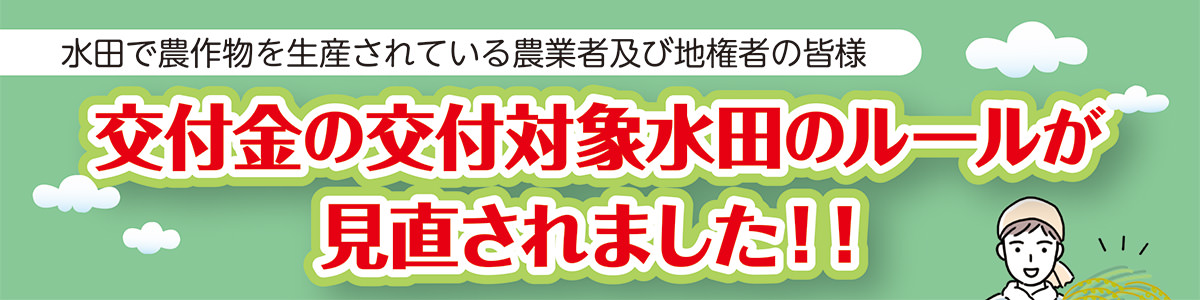
水田政策を令和9年度から根本的に見直す検討を本格的に開始
- 水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換し、麦・大豆・飼料作物については水田、畑に関わらず、生産性向上に取り組む者への支援へ見直すべく検討することを農林水産省から示されました。
- 令和9年度以降は、作物ごとの生産性向上等への支援を検討しているため、水田機能の確認を目的とした「5年水張りの要件」は求められません。
- 今のところ、新制度の詳細は未定ですが、今後、国において、令和9年度に向けた水田政策の根本的な見直し内容が示されてくることとなります。
交付対象水田の範囲について交付対象水田の範囲について
交付対象から除外される農地の基準(平成29年度における見直し)
- 現況において非農地に転換された土地又は転換が確実と見込まれる土地
- 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付を行うことが困難な農地(たん水設備畦畔等無し、用水供給設備無し、撤去困難な施設設置有)
- 平成30年度以降3年間連続して作物の作付が行われておらず、その翌年度も作付が行われないことが確実な農地
5年間に一度の水張りの要件に係る規定(令和7年4月改正)
改正前
以下の両方に該当すること。
- たん水管理を1か月以上実施したことの確認
- 連作障害による収量低下が発生していないことの確認(売上伝票・作業日誌等)
改正後
以下のいずれかに該当すること。
- たん水管理を1か月以上実施したことの確認
実施にあたり地域農業再生協議会の確認を受けるものとします - 令和7年度又は8年度において、連作障害を回避する取組を実施したことの確認
根拠書類等を農業者が作成・保管し、地域農業再生協議会からの求めに応じて提出します。
以上の現行ルールは令和7年度、8年度まで引続き適用されます。
「5年水張りの要件」を1か月以上のたん水管理(水を張ること)で対応する場合の留意点
- 確認については、従来どおり、地域農業再生協議会が行います。
- 水を張る順番や期間は現場の状況を踏まえつつ、隣接する圃場の作付状況等にも注意してください。
- 確認の回数として、たん水期間中に1か月以上あけて2回実施します。
- 水田機能の確認として、一区画全体で判断しますので圃場の部分的なたん水状態であった場合は、「水張り」と認められません。
- 確認の時期については、令和4年度以降の5年に1回、地域における輪作体系を踏まえつつ、適切なタイミングで実施します。
連作障害を回避する取組で対応する場合の留意点
連作障害を回避する取組の具体例
土壌改良資材・堆肥やもみ殻などの有機物の施用
| 土壌改良資材 | 石灰、ようりん、ケイカルほか、地力増進法で定められたもの |
|---|---|
| 有機物の施用 | 家畜ふん、堆肥、もみ殻、米ぬか、ふすま、魚かす、油かす、稲わら、おがくず、汚泥、食品残渣など |
土壌に係る薬剤の散布や後作緑肥の作付、病害虫抵抗性品種の作付け等
| 土壌に係る薬剤 | クロルピクリン、D-D、MITCなどの成分を含む土壌消毒剤、カラスムギなど連作で問題となる難防除雑草に効果の高い除草剤など。 |
|---|---|
| 後作緑肥 | ライ麦、ソルガム、ヘアリーベッチなど、農研機構緑肥利用マニュアルを参照のこと。 |
| 病害虫抵抗性品種 |
連作により発生が助長される各種病害虫の被害を軽減する品種。
|
その他
地域再生協議会等が認めた取組
連作障害を回避する取組の実施を証明する根拠書類とは
- 農業者が作成する作業日誌や栽培管理記録簿、写真(圃場、時期が特定できるもの)等
- 当該作業に用いた資材の入手状況が分かる購入伝票等
- 交付申請書様式第1号Aの「③環境と調和のとれた農業生産の実施状況」の欄にチェックマークがあれば、令和7年度又は8年度に求める土づくり等の「連作障害を回避する取組」を実施したものとみなします。
- 水田の取扱いについては、地権者と耕作者の皆様で十分に協議してください。
- たん水管理(水を張ること)を実施する場合は、事前(実施前)に各市町村の地域農業再生協議会にご連絡ください。